「言葉が足りない」ことで生まれる現代の危機
先日、作家の石井光太さんの講演で「子どもの言葉の危機と回復」というテーマのお話を聞きました。
そこで改めて、今の子育てにとって“言葉を育てる”ことの大切さを感じました。
石井さんは、現代の子どもたちは「自分の気持ちを適切に言葉にできない」まま育っているといいます。
本当は少し悲しかっただけ、寂しかっただけなのに、
「死にたい」「殺したい」と極端な言葉で表現してしまう子どもたち。
気持ちを整理し、表現する力(=国語力)が弱くなると、行動のコントロールも難しくなる。
それが今、社会全体の課題にもなりつつあります。
家庭の会話が「言葉の土台」を育てる
言葉は、学校の国語の授業だけで育つわけではありません。
むしろ、家庭での日常会話が一番の土台になると石井さんは強調されていました。
例えば、
- 「夕日ヤバイ!」ではなく「夕日がきれいだね」と感じたままを素直に言葉にする。
- 管理・命令型ではなく、「どう思う?」「どんな風に感じた?」と問いかける。
こうした日々のやりとりが、自分の気持ちを言語化する練習になります。
実際、3歳の時点で家庭の会話量によって言葉の蓄積に3〜10倍もの差が生まれているそうです。
子どもの言葉の力は、親の言葉の使い方に大きく影響されることを知りました。
成功体験よりも、まずは「安心感」を育てる
今の時代は、早く成功体験を積ませようと焦ってしまいがちです。
でも石井さんは、こう教えてくれました。
自分はこのままでいい。必要とされている。
そんな「根っこの安心感(自尊感情の土台)」が先に必要。
成功体験(かけっこで1位、テストで満点…)は、
土台の安心感があってこそ本当の自信になります。
「成功させなきゃ」よりも、まず「あなたがいてくれるだけで嬉しいよ」と伝えること。
日々の声かけが、子どもたちの心の土台を作っていくのだと感じました。
親ができる4つの習慣
では、親として今からできることは何か。
石井さんは次の4つを挙げられていました。
① 問いかけを増やす
「どう思う?」「なぜ?」と考えを引き出す声かけ。
② 想像の世界を楽しむ
「そんな発想も面白いね!」と自由なイメージを肯定してあげる。
③ 親が豊かな言葉を使う
嬉しい、驚いた、怖かった…自分の感情を素直に表現する姿を見せる。
④ 親が学ぶ姿を見せる
読書や勉強を楽しむ姿は、自然と子どもたちにも伝わる。
親の姿が、子どもに伝わる
スマホ育児が増えている背景には、「親も常にスマホを見ている」という現実があります。
石井さんの言葉が印象的でした。
子どもは、親がしている行動をかっこいいと思っている。
本を読んだり、誰かと会話したり、自分が楽しむ姿を日々の中で見せていく。
それが、子どもたちの「言葉を育てる環境」につながっていくのかもしれません。
まとめ|言葉は生きる力
言葉は、人が生きていく上での**「武器」であり「支え」**です。
SNSや動画だけでは育たない“言葉の力”を、
親子の何気ない日常会話の中から、少しずつ育てていきたいと思います。
心揺さぶられる体験をすることで、つい人に話したくなるそうなので、いろんな体験を子どもたちと一緒に楽しめたらいいなと思いました。
今回の講演を通して、私自身を振り返る良いきっかけにもなりましたが、同時に反省点もたくさん見えてきました。
**「まずは親である私が、言葉を丁寧に使うこと」**を心がけたいと感じています。
(正直、高校生の頃から「ヤバイ」という言葉は日常的に使ってきたので…まずはこの言葉を控える努力から始めてみます。)
また、小学4年生ごろからは、文章問題の多くが抽象的な表現に変わるそうです。
想像できない子が増え、文章は読めても内容を理解できない──そうして学力に差が生まれていくタイミングになると聞きました。
算数・英語・理科…すべての教科に国語力は関わってきます。
私もこれから子どもたちと一緒に、豊かな言葉を育てていきたいです。
maru
💡合わせて読みたい記事はこちら💡
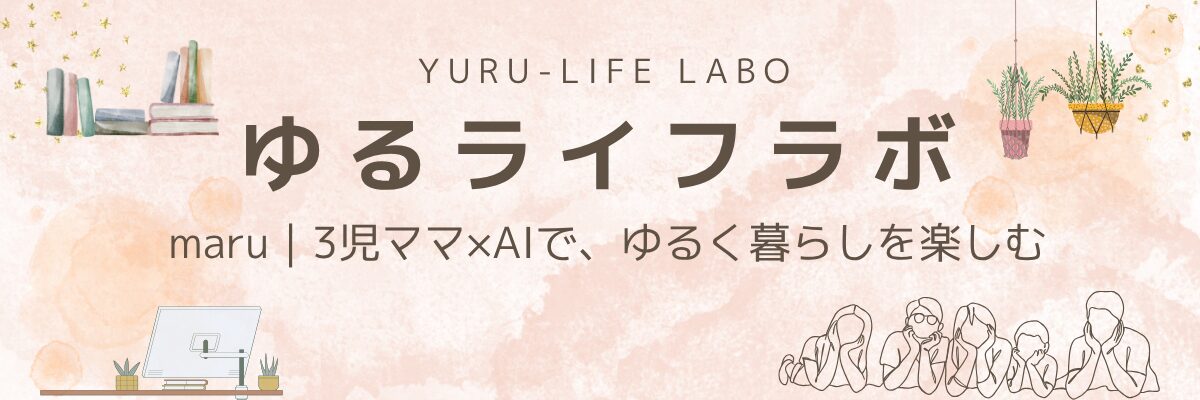



コメント